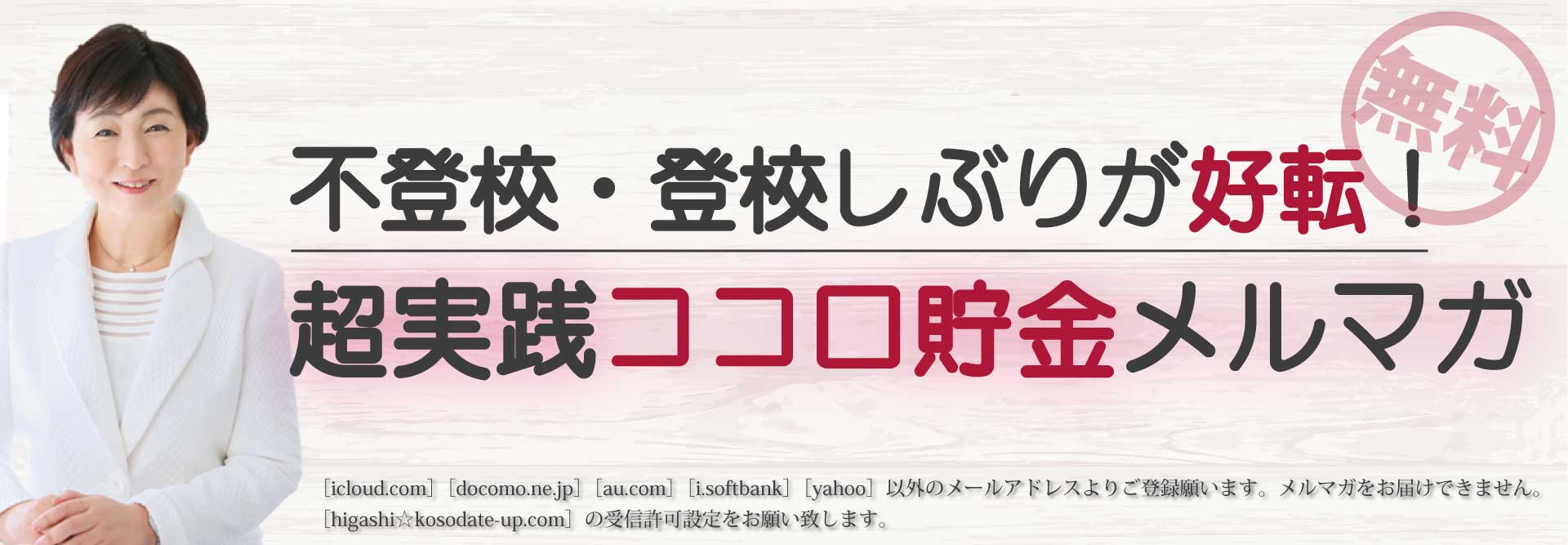小さい子どもに癖に…
「えいきゅうにきえてくれる?」
「ざけんなよ!」
「知らんし」
リコちゃんは、まわりがびっくりする言葉を言います。
りこちゃんのまわりのおともだちも、まわりの大人も、びっくりします。
他のママが、びっくりして、リコちゃんばかりか、リコちゃんと一緒にいるリコママに対して、引き避けるような態度を示すのです。
この前も、こんなことがありました。
リコちゃんとママが公園の砂場で遊んでいたときのことです。
同じ公園でよく見かける女の子が砂場に来ました。
その女の子は、砂場で山を作ろうと、家からかわいいスコップを持ってきました。
スコップは、柄が緑で、砂をすくうところがピンクで、女の子のお気に入りです。
さっそく、女の子は、砂をすくって、山を作り始めました。
それを見ていたリコちゃんは、いきなりそのスコップを、女の子の手からもぎ取りました。
女の子はびっくりして、言葉が出ません。
そんなびっくりの様子をお構いなく、まるで、自分のスコップであるかのように、山を作り始めます。
女の子は、自分のスコップが持っていかれたことで、リコちゃんのスコップを取り返そうとします。
リコちゃんは、つかんだスコップを話そうとしません。
そればかりか、こんなことを言い出しました。
「リコちゃんの」
「スコップ、リコちゃんの」
「ダメ、持っていちゃあダメ」
そういって、女の子の手をはねつけ、女の子を、砂の上に投げ倒したのでした。
もともと、女の子のスコップなのです。
顔中、砂だらけになりなりながら、口には砂が入ってしまっています。
女の子はなすすべなく、近くのベンチにいたママのところへ、泣きながら行きます。
「ママ、わたしのスコップ」
「スコップ、とられちゃった」
女の子のママは、砂場の方を見ました。
砂場には、リコちゃんとそのママが楽しそうにうちの娘のスコップを使って遊んでいるではないですか。
いそいで、そのスコップが自分の娘のものであることを、伝えようと砂場に行きます。
けんかせずに、今後も付き合うことがあるかもしれないので大事にならないように話します。
「すいません。うちの子どものスコップを、こちらの娘さんが使っているので、返してもらいに来たんです」
「返していただけますか」
すると、リコちゃんはどうでしょう」
「これ、りこちゃんのもの」
「リコのもの」
スコップを離そうとしません。
もう一度、話してみました。
「うちの娘の大事なスコップだから、返してね」
しかし、リコちゃんは、こんな返しようです。
「いやだ、りこちゃんのものだから」
「うざい」
「あっちへ行け」
「しね」
リコママは、リコちゃんの言葉を聞きながら、こう言います。
「おたくの娘さんのスコップっていう証拠があるんですか」
「このスコップ、名前が書いてなくて」
「ここに来た時に、スコップが落ちていたから、もったいないから、リコちゃんに使わせているんです」
「あなたの娘さんも、使いたいのなら、うちのリコちゃんが、砂遊びに飽きちゃったら、貸してあげるけど、どうします」
「いい加減、うざいこと言うのやめてもらえんかなあ」
「うちのリコちゃんに因縁つけて、めんどくさいこと言うのなら、警察呼びますよ」
リコちゃんは、リコママが話しているのを聞きながら、言います。
「りこちゃんは、おちてたのをつかっている」
「うざいから、あっちへ行け」
「けーさつ、よぶぞ」
「・・・・」
スコップの持ち主の女の子も、そのママもとりつくシマがありません。
しぶしぶ、あきらめて、ママは女の子に言います。
「もっと、いいスコップを、買ってあげるから、ごめんね」
ベンチに戻ると、騒ぎを遠巻きで見ていたママ友が集まってきました。
「大変だったね」
「ウチも前に、バケツ持ってかれちゃったことがあるよ」
「ウチは、滑り台で並んでいたら、横入りするだけでなく、並んでいたうちの子を跳ね飛ばして、手を擦りむいたんだ」
「そのときも、苦情を言ったんだけど」
そのときのリコちゃんは、なんも悪びれていなかったんです。
リコママも、うちの子が悪いって一つも思っていない言い草で、
「リコちゃんの進んでいるそこに、あなたの娘さんがいたから、怪我したんでしょ」
「あなたの娘さんがいなければ、うちのリコちゃんがぶつかることもなかったでしょうし、怪我をすることもなかったでしょう」
全然、悪いと思っていないんです。
リコちゃんがいると、こういうことが、四六時中起こるんです。
まわりからは、リコちゃんもリコママも、残念なことだと思われています。
でも、りこちゃんもリコママも、そんなことお構いなしですし、気にすることもありません。
「親の後ろ姿を見て、子は育つ」と言いますが、リコちゃんの場合は、親の姿をまじかに見てそのものから体感してそのまま育っているのでしょう。

どうですか?リコちゃん、素直に育っているでしょう。
リコママは、どう思っているでしょうか。
何も問題ない育ちだと、思っているでしょうね。
ママも、こういったトラブル付きで、育ってきていて困ったことは怒っていないのではないでしょうか。
まわりは大変困っているのですが、気づかない。気づけないのでしょうね。
社会的には、警察とかのお世話になったり養護施設や鑑別所などにも関係したりしていることもあるのでしょうが、それも、人生の一つの調味料と考えていることもあるのでしょう。
いや、何とも考えていないのかもしれません。
社会で、自分の個性を伸ばしながら、より充実させて生きていくには、小さいころに、次の魔法の言葉を身に付ける必要があります。
「ごめんね」
「いいよ」
この3つの魔法の言葉を、小さいころから、どのタイミングでどのように言うのかを、親と一緒に学んでいくことが大事なことです。
リコちゃんが、スコップを使いたくなった時に、
「かして」
「いいよ」
「ありがとう」
で、いけると、スコップの所有関係もはっきりしますよね。
間違って、スコップを使っていた時には、
「これ、わたしのだよ」
「ごめんね」
「すこしかして」
「いいよ」
でいけると、いいでしょう。
どこまでいっても、小さいときに身に付けるべき魔法の言葉。
「ありがとう」
「ごめんね」
「いいよ」
です。
「死ね」
「しね」
「シネ」
「死んでくれる」
「ウザイ」
他にも、ありますね。
これらは、学齢期では、どれも「いじめ」となっていく言葉です。
いじめている気持ちがなくても、「いじめ」と言われた方が感じれば、「いじめ」と認定されます。
何気ないく使っている言葉であるとしたら、どこで覚えたのでしょうか。
多くはまわりにいる大人や兄弟などの家族が話しているのでしょう。
残念なことですね。
もし、我が子が話していたら、ママ自身の言葉遣いを、振り返りましょう。
ひょっとしたら、ママが同じことを誰かに言っているかも知れません。
そういう場合は、もう言わないことです。
夫婦関係でそんな言葉を言っていませんか。
お子さんが聞いていなところだからと思っていても、お子さんはいつのまにか同じように話すのです。
そうでない場合は、「アイメッセージ」で、
「ママは、そんな言い方いやだなあ」とママの気持ちを表明するのです。
そうすることで、周りが、特に一番大好きなママの気持ちが代表して、お子さんに伝わるでしょう。
決してしある必要はないのです。
「ママは、その言い方、嫌だな」
って、言えばいのです
リコちゃんは、利己ではなく、利口な子ですので、まわりの気持ちを自分で感じていけるはずです。
楽しみですね。