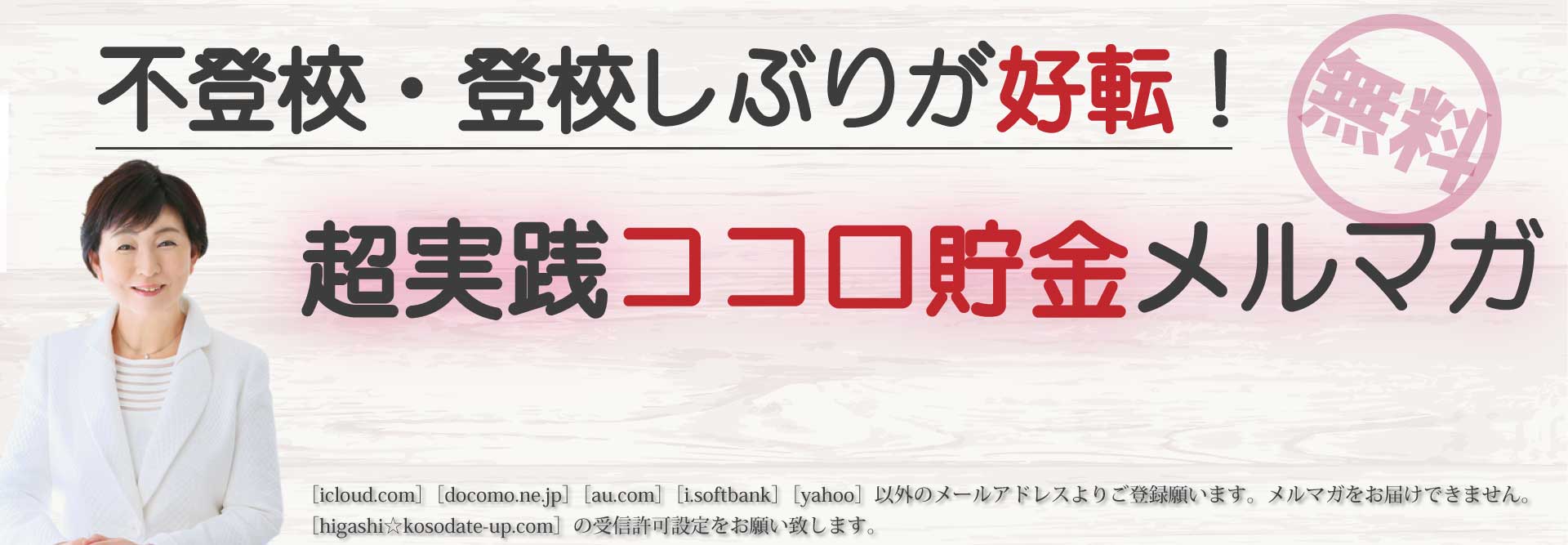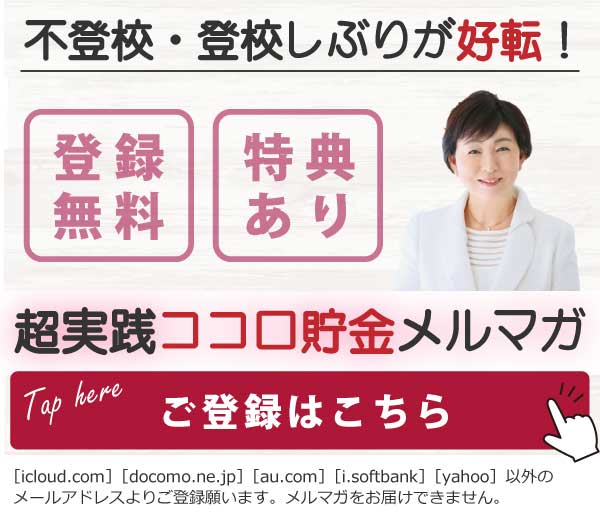体験談
体験談
帰宅後の日課は〇〇〇〇
——ああ、生きている。
仕事から帰ってまず行う日課は、長女の生存確認でした。自室にこもり布団をかぶったまま、決して顔を見せてくれない長女。
「ただいま」と言っても返事はありません。部屋のドアをそうっと開き、全神経を集中させて布団のふくらみを注視します。
かすかな揺れや呼吸音。命の気配を感じると、安堵で緊張がゆるみました。
「犬を飼ってくれたら学校に行く」という彼女の言葉を受けて飼った室内犬がいつも枕もとに横たわっていて、わたしが近づくと怒ってキャンキャン吠えてきます。
鳴き声に追われて退散する無力な自分。この先どうなるのか、母として何をしたらよいのか、もうわからなくなっていました。
——これは何とかしなければ。
危機感をおぼえ、ずっとメルマガを拝読していた東ちひろ先生に助けを求め、子育て心理学カウンセラー養成講座を受講することにしました。

【寺倉じゅんさんのプロフィール】
3人のお子さんをもつワーキングマザー。小学校3年から登校をしぶるようになった長女さんは、中学で不登校に。子育て心理学カウンセラー養成講座を受講したのは、長女さんが高校2年生の頃。
登校しぶりから不登校へ
長女が登校をしぶるようになったのは、小学3年生の頃でした。当時は文字通り「引きずって」学校に連れて行っていました。途中まで迎えに来てくれた先生の車に無理やり押し込み、どうにか登校。
ところが中学生になると体が成長し、「引きずり登校」はできなくなります。鬱々とした、引きこもりの生活がはじまりました。
仕事があるので、長女を残して家を出なければなりません。ただいまと帰ってきても、反応はゼロ。自室にこもり常に布団をかぶっている状態で、顔を見せてくれない、声を聞けない、お風呂に入っている様子もない。勉強なんて言わずもがなです。
学校の先生が週に数回訪問してくれて、枕もとで「顔見せてくれるか~」と声をかけても、絶対に出てこようとしませんでした。
それでも当初は、どうにか復帰させようと必死で試みました。「いつまで寝てるの」「なんでそんなことするの」と声を荒らげて詰め寄ったこともあります。
結果は、事態を悪化させただけ。こちらが強く出ると、長女も強く反発します。
あるときは部屋の鍵を閉め、さらにドアが開かないようにテレビを移動して、徹底抗戦の構えをとられました。息子と一緒にドアを壊して中に入りましたが、ドアが壊れたときでさえ布団から出てきませんでした。
もっとひどくなるとカッターで家族写真を切り刻んだり、壁に「〇ね」という文字を綴ったり。
カッターを持ち出したわが子を見て「刺激を与えてはいけない」と強く感じました。脳をよぎったのは、まるでTVドラマにあるような最悪のシナリオ……。
何か葛藤があったとき、口にできずに激しい行為で発散させてしまうタイプなのだ。
そう気づいてからはますます手詰まりとなり、放っておく以外にできることがなくなっていました。
鉛のように重い気持ちを抱えながら、時だけが過ぎていきます。
今日はごはんを食べただろうか。
不安のもとは学校に行けないことではなく、命の心配へと変容していきました。
言いながらさすってみたところ、嫌がりません。これはいいかも! と手応えを感じて続けていくと、何となくそこから長女が変わっていった気がします。
かすかな兆し
ほとんど登校せずに中学を卒業した長女は、勧められるままに通信制の高校に入学しました。
通えなくても、卒業さえしてくれればいい。
その頃にはもう多くを諦めていて、叱ることもなく、過分な望みは抱かなくなっていました。
少しでも外の空気に触れてほしくて、ときどき声をかけました。
「〇〇に行くけどついてくる?」
「ハンバーグ食べに行こか」
偏食な長女の大好物はハンバーグ。気分しだいでついてくるようになっていました。
ココロ貯金と出会ったのはちょうどその頃です。長女は高校2年生。不登校になってから4年が経過していました。子育て心理学カウンセラー養成講座を受講して、迷い葛藤し娘を放置するしかなかった自分を、丸ごと承認してもらえた気がしました。
。
そんなある日、初めて長女の笑い声を聞きました。オンラインゲームをしながら誰かと話しています。ケラケラと明るい笑い声。
「お姉ちゃんが誰かとしゃべってる!」
妹も驚きの声をあげます。
笑うんや。しゃべるんや。こんなして笑う子なんや。
熱いものがこみあげました。
バリケードの崩壊
長女が高3になったとき、転機は突然訪れました。家でパソコン仕事をしていたところ隣にやってきて、堰を切ったように泣き出したのです。
「将来が不安なんや」
ひっくひっくとしゃくりあげながら、精神科に連れて行ってほしいと懇願されました。
それまでまったく話さなかった子が初めて見せた、激しい感情。
「よう話してくれたね」
“精神科”という言葉にどきっとしながらも、むせび泣くわが子を抱きしめました。
「お母さん、ずっと心配してたんやで」
「ずーっと何を考えているのか、どうしていいのかわからへんかってな、ごめんな」
よしよしと頭をなで背中をたたきながら、精一杯の言葉をかけ続けました。
突然の告白に落ち着いて対処できたのは、ココロ貯金を学んでいたからだと思います。しっかりした受け皿がわたしの中にあってよかった! 心からそう思いました。
外の世界へ
長女が高校を卒業して専門学校に入ると「ばんばんココロ貯金ができる!」とはりきっているわたしがいました。
まずはお弁当。高校に通学しなかった彼女には「母の弁当」を食べた期間がありません。お弁当づくりは苦手なのですが、がんばって毎日作りました。また、たった15分の道のりですが駅まで送り迎えすることに。必然的にラインのやりとりも増えます。「今から来て」「これから出るよ」「おかえり」「おつかれさん」。
接触の回数を増やして名前を呼びかけ、「あなたを見ているよ」というメッセージを伝えます。無理に会話しようとはせず、彼女が話してかけてきたときは全身で聴きました。
入学したのはいいけれど、ちゃんと行くんかな。
正直心の底には疑いがありました。しかしなんと! 無遅刻、無欠席で学校に通いはじめたのです。
テスト前にはちゃんと試験勉強して、成績は全教科に「優」の文字。これには驚きました。
毎日お風呂に入るようになったので髪をドライヤーで乾かしてあげたり、おしゃれっ気が出てきて一緒に洋服や化粧品を買いに行ったり。年頃の女の子と母親らしい交流ができるようになりました。
2年生に進級する際には特待生の誘いを受け、自分の意思で手続きをしてきました。申請理由は「お母さんに負担をかけたくないから」。想像もしなかったうれしい言葉でした。
気をつけていたのは、少々イラッとすることがあっても怒らないこと、声を荒らげないこと。
敏感で溜め込みがちな子。せっかく開いてきた心を再び閉じられたらたまったものではないからです。いきなり「これで安心、万々歳」となるわけではなく、少しずつ少しずつ、手探りで前進していきました。
卒業の日。
ステージ上には、学年で一人だけ選ばれる「学園長賞」を授与された長女の笑顔がありました。
春の光に照らされた彼女の顔は明るさに満ち、いつまでも見つめていたいと思うほどキラキラと輝いていました。
寺倉じゅんさんが実践したココロ貯金
・感情にまかせて怒らない、声を荒らげない
・「ハンバーグ食べに行く?」など好物を使った声がけ
・「よう話してくれたね」と受け入れる
・心をこめたお弁当
・駅までの送迎、ラインのやりとりなど、接触の機会を増やす
・無理に会話しようとはせず、話してかけてきたときは全身で聴く