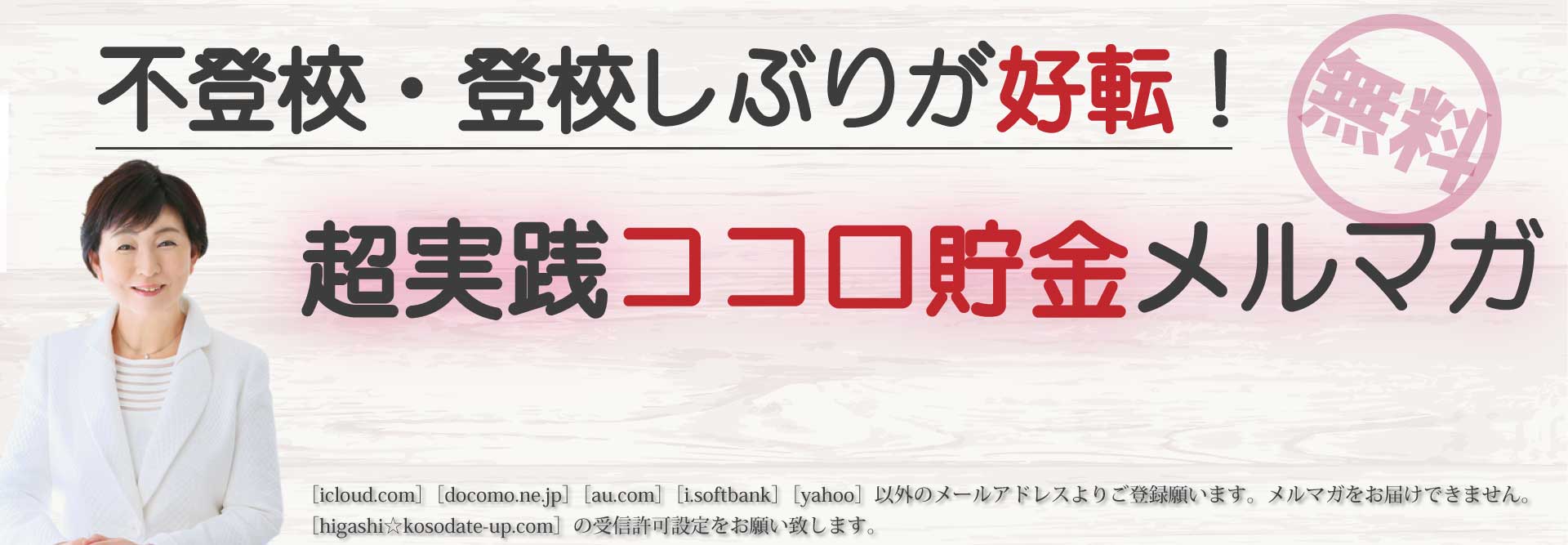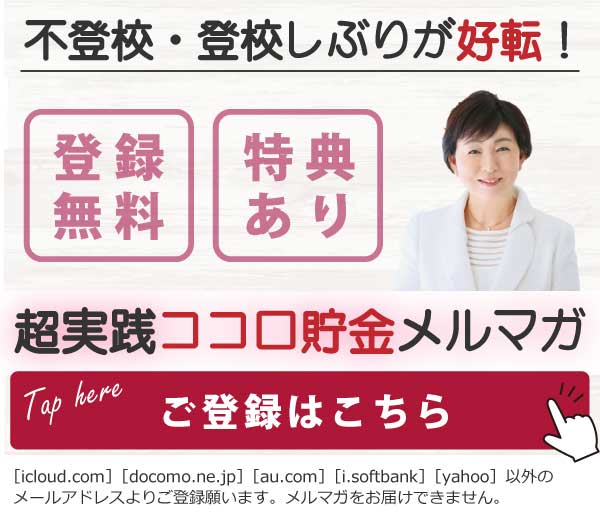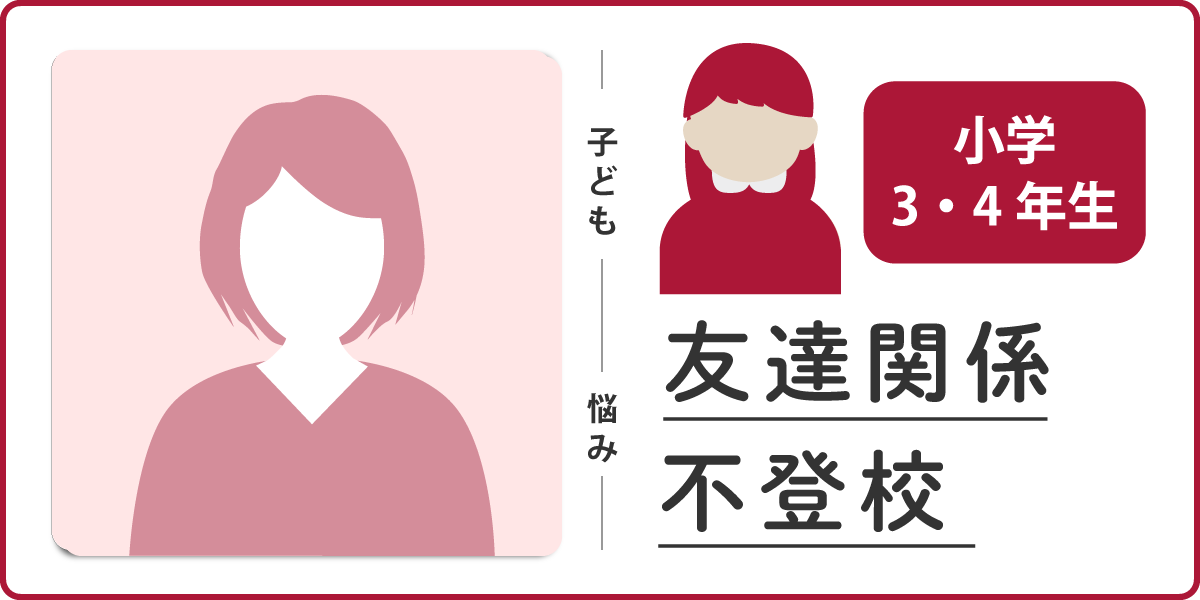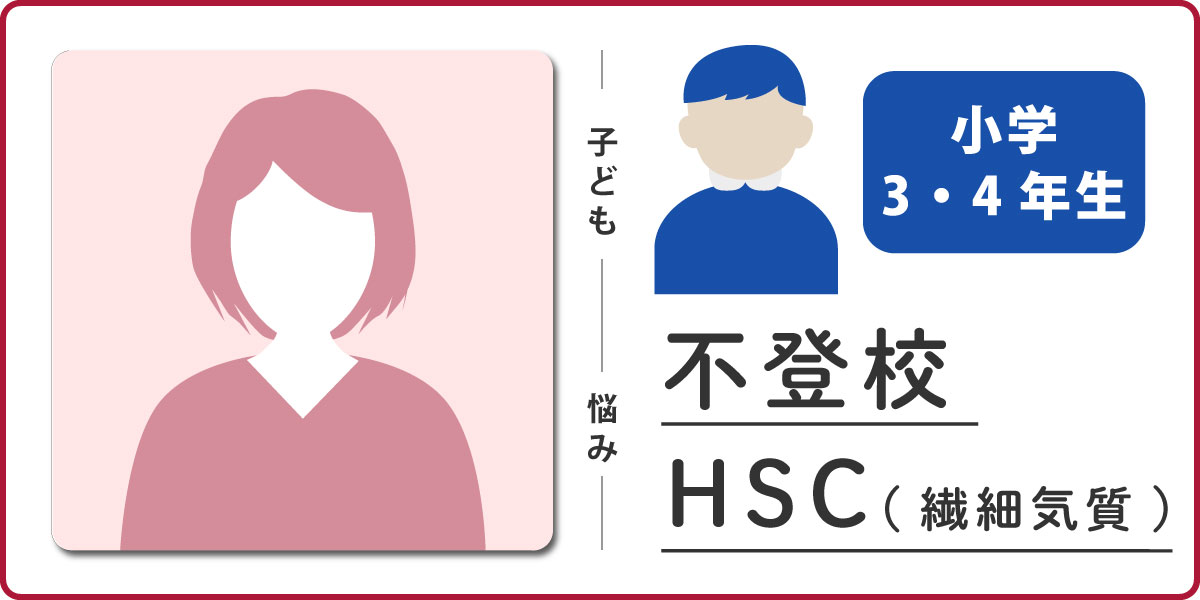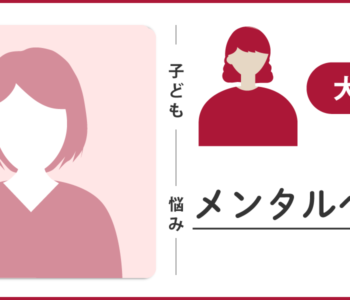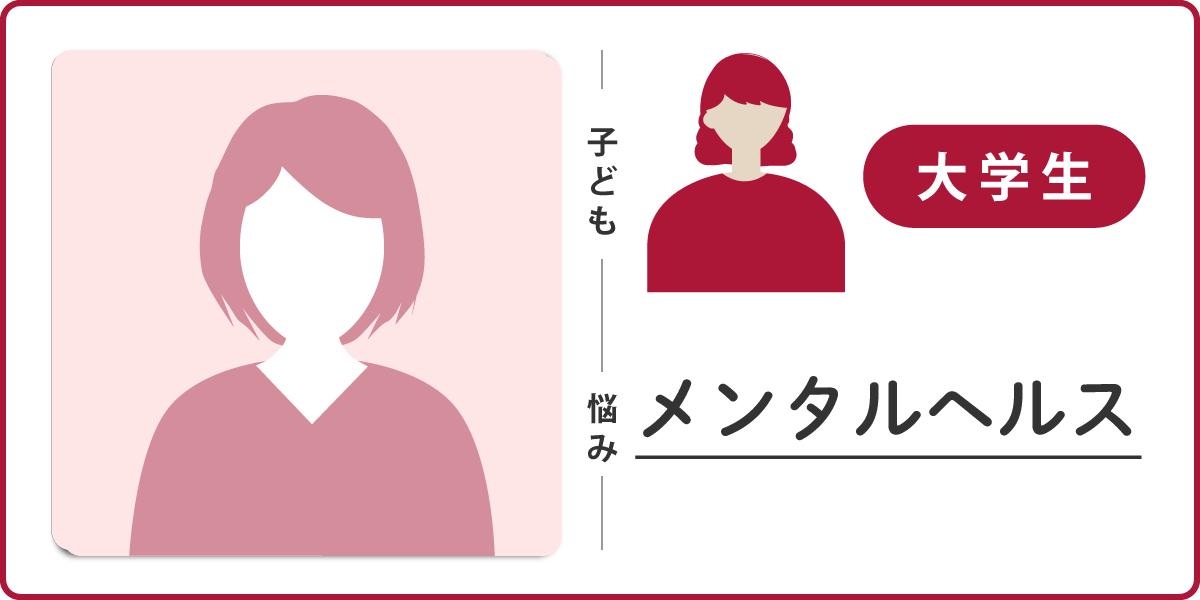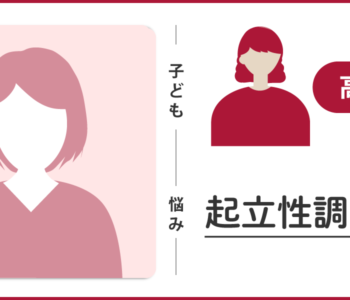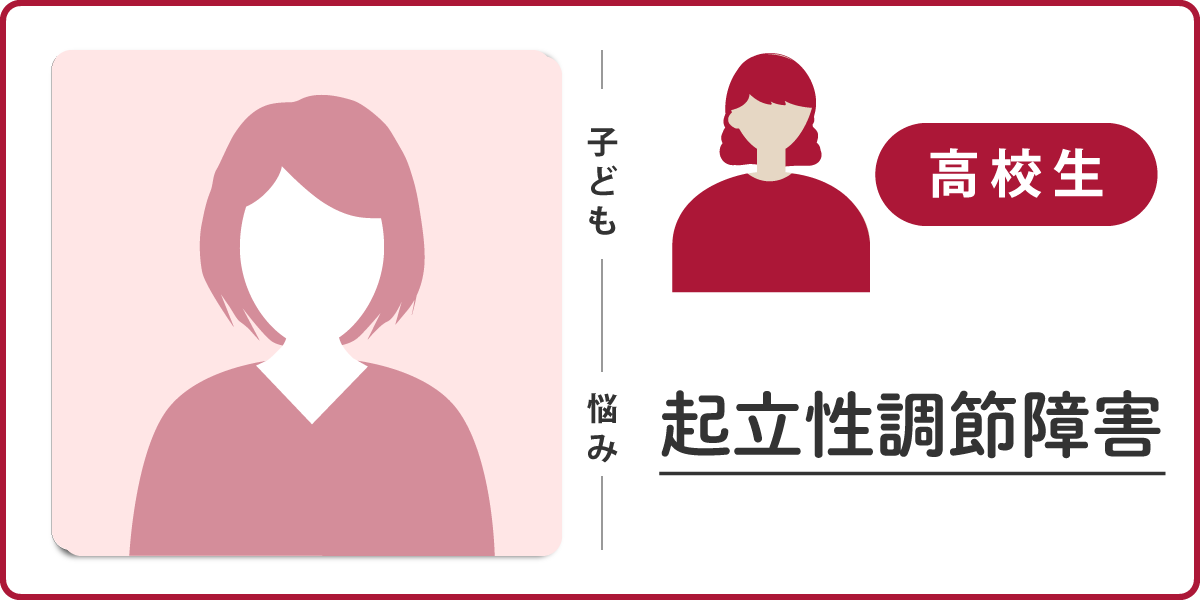vol.27 AS…
◆学校はおばけ屋敷
息子が小学校に入学した年は、コロナ禍の真っただ中でした。
3か月の休校からはじまった小学校生活……。
「明日は学校あるの? ないの?」
「ぼくは保育園生なの? 小学生なの? 全然わかんないよ」
「ママ、ママ、ぼくはどうしたらいいの?」
ルーティンが大好きな息子にとって、先の見えない毎日はとても苦しいものだったようです。不安が積み重なり、やがて混乱へと変わっていきました。
通常登校がはじまってもパニック状態はおさまらず、毎日登校をしぶります。わたしも仕事があるので、息子の手を引っぱって無理やり登校させていました。
ところが、やがて——
校舎を見るだけでブルブル震えるようになってしまったのです。
「学校はお化け屋敷だ。こわいから行かない」

【宮治ゆみさんのプロフィール】
3人のお子さんをもつワーキングマザー。
まん中の長男さんは現在小学6年生で、ASD・ADHDの特性をもつ。
子育て心理学カウンセラー養成講座を受講したのは、長男さんが小学2年生の秋。
◆荒んでいく心
「学校は、何があっても行くもの」
当時のわたしはそう信じていたので、“不登校”をすんなりと受け入れることはできませんでした。同居している両親も気持ちは同じ。
家族みんなに「学校に行きなさい」と言われ続けた結果、息子はさらに心を閉ざし、学校への拒否感は日に日に強くなっていったのです。「行きたくない」は「行かない」に変わり、息子は家に閉じこもるようになりました。
家で過ごすようになっても、息子の心はどんどん荒れていきました。
お姉ちゃんと弟にちょっかいを出してはケンカになり、おじいちゃんに暴言を吐いて叱られる。
レゴブロックを、まるで豆まきのように部屋中にばらまいてしまったこともありました。人を傷つけ怒らせるような言葉を、わざと使っているような印象なのです。
そうかと思うと、幼い1年生らしからぬ悲しい言葉を口にします。
「困らせちゃってごめんなさい」
「ぼくなんて、生きている価値がない」
胸がしめつけられました。
この子の自己肯定感をこんなにも下げてしまったのは、母であるわたしなのかもしれない——。
それでも、やっぱり学校には行ってほしい。
先生やお友だちとの関わりの中で、たくさんのことを感じて学んでほしい。
願いと現実のあいだで、わたしの心は揺れに揺れていました。
迷いと葛藤の中でもがいていたとき——出会ったのが、ココロ貯金でした。
◆シンプルだったココロ貯金
すがるような思いで東ちひろ先生の本やブログを読み、無料カウンセリングにも参加、3カ月の子育て心理学カウンセラー養成講座を受けてみることにしました。
「えっ、これだけでいいの?」
講座を受けて驚いたのは、ココロ貯金の方法が想像以上にシンプルだったこと。
こんな簡単なことで本当に変わるのかと、正直、半信半疑でした。
それでも、まずはやってみよう。
「聴く」「触れる」「認める」
3つのココロ貯金を、わたしなりに、できることからはじめてみました。
今ふり返れば、最初に変わったのは息子ではなくわたしだったと思います。
“学校に行っていない”ことしか見えていなかったわたしでしたが、ココロ貯金を実践していくうちに、 “それでも、あなたが大好き”なのだと伝えられるようになりました。
すると、いつの頃からか息子の目が丸くなり、情緒も落ち着いていったのです。
このときの体験は、子育て心理学協会ホームページの「体験談」に載せていただきました。不登校をきっかけに仕事と家庭が回らなくなった当時の葛藤や、働きながら実践した「リモート・ココロ貯金」について書いています。
◆スモールステップ
今回は、少しずつできることを増やしていった息子の歩みをお伝えしようと思います。
2年生のときは、本当に無理のないペースで“半歩ずつ”学校に近づいていきました。
- 家庭訪問
ありがたかったのは、支援員の先生が週に1度、家庭訪問を続けてくださったことでした。
「来るな」
「出ていけっ」
当初は全身で拒否していた息子でしたが、大好きなポケモンを作ってくれたり手紙を書いてくれたりする先生に、少しずつ心を開いていきました。
「週に一回だったら、来てもいいよ」
などとえらそうに言って、先生の訪問を楽しみにするようになりました。
- 校門前を通って散歩
ココロ貯金や先生の家庭訪問に救われて、息子の情緒は少しずつ安定していきました。やがて外にも出られるようになったので、よく一緒に散歩しました。
そんなときはひと工夫。
わざと校門前を通るルートで郵便局に行ったり、アイスを買いに行ったり。
先生が校庭に出るタイミングを教えてくださり、時間を合わせて体育の授業を見学することもありました。
「先生、手を振ってくれなかった!」
プンプンしながらも、“学校”への関心が少しずつ高まっていきました。
- 忍者登校
ある日、息子が言いました。
「誰にも会わないなら、ぼく、学校に行ってもいいよ」
支援員の先生が、“学校での楽しいこと”を上手に伝えてくださっていたのです。
「じゃあ夕方、誰にも会わない時間に行ってみる?」
こうして、はじまったのが“忍者登校”。誰もいない時間帯にサッと行って、ササッと帰ってくるスタイルです。それが「給食を食べたい」という息子のひと言をきっかけに、給食の時間だけ学校に行くようになりました。
先生が用意してくださったのは、保健室の隣の静かな個室。カーテンとドアを閉めれば、完璧な“安心空間”が完成します。
こちらから無理に促すことはせず、見守っていると——
気づけばカーテンのすき間から校庭をのぞいていたり、閉めていたドアを少し開けて廊下の様子を見ていたりしました。
そのうちに廊下を通って給食を下げられるようになり、廊下で誰かとすれ違えば挨拶し、保健室にいる子とおしゃべりをする姿も見られるようになったのです。
「せっかくだったら保健室で食べてみる?」
調子のよい日は、保健室での給食タイムを楽しめるようになっていました。
- 交換絵日記
「友だちと遊びたい」
ある日、息子がぽつりと言いました。
当時は同学年の子との交流は全くない状態。
「どうしたら友だちと遊べるかな?」と一緒に考えながら、少しずつアクションを起こしていきました。
まずは校門から手を振ってみること。
次は先生に協力してもらって、絵日記を交換してみること。
息子がカブトムシの絵を描いたときに、クワガタの絵を返してくれた男の子がいました。
「きみ、昆虫好きなの?」
一枚の絵からつながりが生まれ、ある日、その子が学校の先生と一緒に家を訪ねてきてくれたのです。息子は少し照れながら玄関にカブトムシを持ってきて、うれしそうに話をしていました。
- 体育に合流
いつもの散歩の途中、体育の授業を見学していた息子がつぶやきました。
「体育、出たいな」
これはチャンス!
体操着にも着替えずに、私服のまま授業に参加させてもらいました。
その日の体育は4時間目だったので、給食の時間に突入。クラスの子たちに「給食は教室で食べようよ!」と誘われ、そのまま教室へ——。
このように先生やお友だちに助けられながら、息子はいつの間にか「学校はおばけ屋敷」だなんて言わなくなっていました。
・調子のわるい日は「別室登校」
・少し元気な日は「保健室登校」
・もっと調子がよい日は「教室登校」
その日の体調に合わせて、無理なく登校できる場所を選べるようになっていったのです。
◆ASDとADHDと診断され、薬を服用
2年生の夏、息子に大きな転機が訪れました。
発達検査を受けた結果、ASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如・多動症)という診断がついたのです。この診断により、放課後デイサービスの利用が認められ、徐々に人との交流や行動範囲が広がっていくことになります。
また、ADHD の衝動性や多動性を抑えるためのお薬を処方されました。
ところが、どうもうまくいきません。服用すると昼間に強い眠気が出てしまい、起きられずに学校を休む日が続きました。情緒を落ち着ける薬を飲むと、学校に行けない――本末転倒な状況に、親としても戸惑いました。
何度か主治医の先生とすり合わせした結果、2種類処方されていたうちの一方は、体質に合わないという結論に。もう一方の薬だけに絞り、「どのタイミングで、どの量を飲むか」を少しずつ調整していきました。そして、夜寝る前に服用すると翌日の血中濃度が安定することがわかり、ようやく息子に合ったスタイルが整っていったのです。
◆ココロ貯金で自然に減薬
ココロ貯金と薬の服用を続けていった結果、少しずつ教室で過ごせる日が増えていきました。3年生になると、おばあちゃん、おじいちゃん、夫……とわたし以外のつきそいも可能になり、わたしの負担感はぐっと軽くなっていきました。
「薬は最低限の1ミリでいいよ。飲まなくてもよいけれど、どうする?」
主治医の先生にそう言われたのもこの頃のことです。
いきなり止めてしまうのは少し不安。息子自身も飲んでいた方が安心する感じだったので、お守り代わりに少量だけ服用を続けることにしました。
つきそいが必要な時間は徐々に短くなり、送っていけば帰りは自分で帰ってくる日も増えていきました。ただ「ランドセルはいやだ」という不思議なこだわりだけは、なかなか手放せずにいました。
ところが、4年生のお正月。
「ぼく、ランドセルしょっていく」
突然宣言した息子は、冬休み明けから、ホコリをかぶっていた“ピカピカのランドセル”で登校するようになりました。以来ずっと、ランドセルで学校に通っています。
また、朝から下校時刻まで学校にいられるようになったのも4年生でした。
滞在時間が増えたぶん負荷も大きくなったようで、一時的に「ママきいて!」と不安を吐き出す場面が増えました。
でも、「そっかそっか」と寄り添いながら聴いていると、息子の気持ちはだんだんと落ち着いていくようでした。
3年生、4年生と進むにつれて、学校での負荷は確実に増えていったので、薬を止めるタイミングについてはなかなか踏み切れずにいました。
それでも、ランドセル登校を半年続け、息子も自信がついたのかもしれません。
小学5年生の夏。
主治医の先生が「もう薬を止めていいんじゃない?」とたずねたとき、息子はまっすぐに答えたのです。
「ぼく、もう薬はいらない」
こうしてついに——
薬を卒業したのです!
◆息子の今
息子は現在6年生。
薬を止めて9カ月が経ちましたが、落ち着いた日々を送っています。
授業には毎日参加。
例えば、6時間授業のうち1コマだけしんどいときにはその時間だけ保健室に避難して、うまく調整しています。
「今日の社会、あまり好きじゃないから保健室に行きます」といった調子で、朝、先生に宣言するらしいのです。発達特性のある子らしいな、と思うのですが。
6年生にもなると、まわりの子たちも「なんで保健室行くの?」などとは言わなくなりました。
息子の事情を理解して「そういう子なんだ」と受け入れてくれているのを感じます。息子が「ありがとう」をよく口にするからか、クラスでもあまり浮いていないようです。
「移動教室は苦手」
「こういうときは不安」
しっかりと言葉で伝えてくれるので、学校へフィードバックしやすく、わたしも無理なく調整役を担えるようになりました。
先生に送っていただいた1週間の予定をもとに、息子は予定を組んでいきます。
「火曜日はしんどそうだから、ここまでにしよう」
「この日は早退して、放課後デイサービスに行こう」
自分で考え、事前に伝えてくれるので、仕事も調整できるようになりました。
どうすれば心地よく過ごせるのか、息子自身が自分のトリセツをわかってきたように感じます。
サポートが欲しいときにはSOSを出せるようになった息子の姿が、とても頼もしく映ります。
小学校に入学したばかりのあの頃、あんなに苦しんでいた日々が嘘のように、息子は今、自分らしく学校に通っています。お友だちとの関係も親子関係も、穏やかであたたかいものになりました。
——ああ、心を育てるって大事なのだな。
ゆっくり、でも着実に歩んできた息子から、たくさんのことを教わった気がします。
◎宮治ゆみさんが実践したココロ貯金◎
・学校の先生と連携
・細やかで丁寧なスモールステップ
・息子さんの意思を尊重した自然な減薬