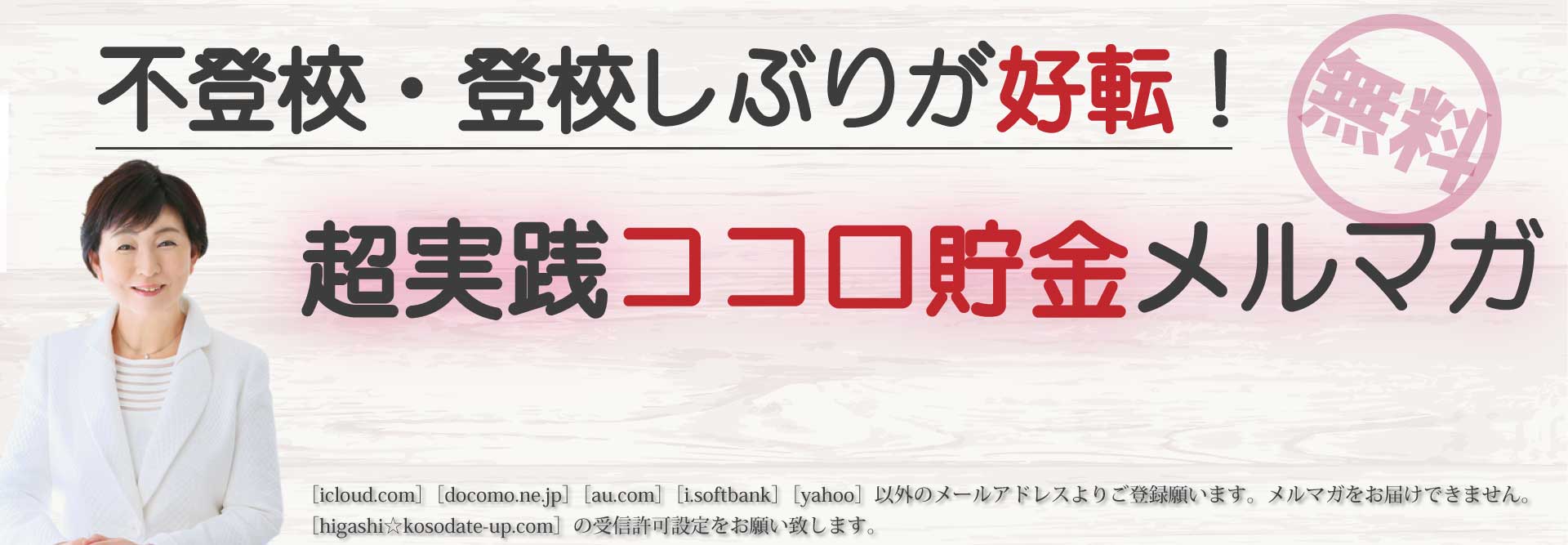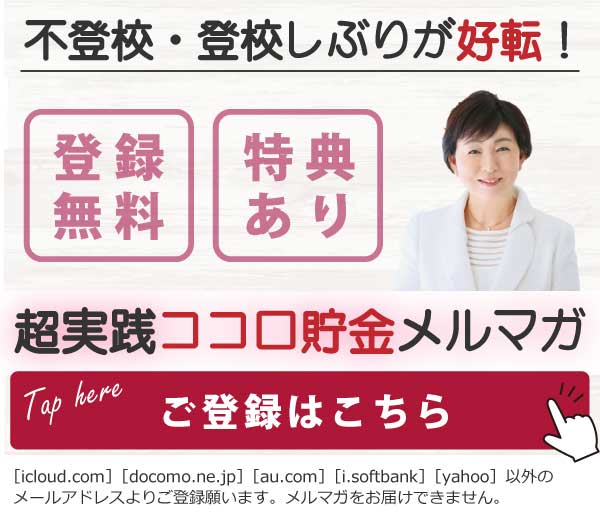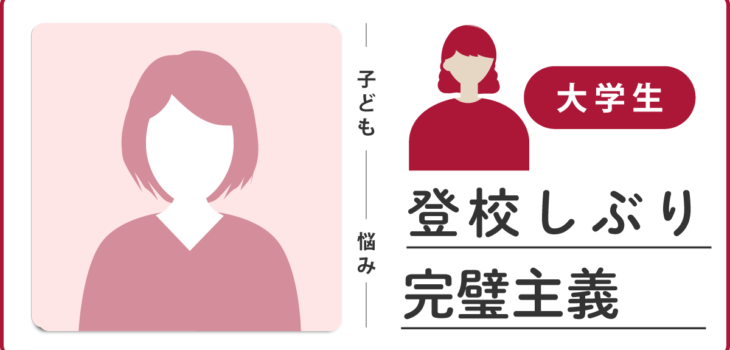 体験談
体験談
ネガティブなメモ
「生きているのがつらい」
ふと気になってのぞいた娘のノート。
そこには、胸を締めつけるようなネガティブな言葉が並んでいました。
中学校に行けない日々のなかで、娘が綴ったもの。 まるで、生きる意欲そのものを削るような言葉たち。
ページをめくるたび、暗い未来ばかりが心をよぎり、胸がぎゅっと痛みました。
——どうしたらいいの?
答えが見つからないまま、不安を抱え続けた中学生活は、静かに幕を閉じました。

【お母さんのプロフィール】
大学1年生のお嬢さんと高校1年生の息子さんのお母さん。お嬢さんは中学時代不登校で、通信制の高校を卒業。子育て心理学カウンセラー養成講座を受講したのは、お嬢さんが大学生になってまもない頃。
消えない不安
中学を卒業した娘は、通信制の高校へ入学。
「今日は行きたくないから休む」と、登校する・しないを自由に選べるシステムがうまくフィットして、無事卒業できました。その後は、短大よりもゆっくり学べそうだと大学に進学……。
このように書くと順調のように見えますが、不安はなくなりませんでした。
神経が細く生きづらさを感じやすい娘です。
はたから見れば普通の大学生に見えたはずですが、娘の“我慢のコップ”が今にもあふれてしまいそうな危うさをいつも感じていました。
課題をしながら「もうやだあ」と泣き出したり、朝、支度しながら「ああーーっもう時間ないっ」とヒステリーをおこしたり。朝 5 時起きで課題を終わらせた後、「10 分だけ寝てくる」と寝室に行ったまま起き
られないこともありました。消耗が激しく、見るからに不安定。
娘は「こうありたい」「こうあるべき」というこだわりが強く、あるべき姿に向かってアクセルをどんどん踏むタイプ。スピードに耐える体力も精神力も持ち合わせていないので、最終的にダウンしてしまうのだと思います。
⾧くても 15 時までで週 3 回程度の通学ですんだ通信制高校の生活と、大学生活はまったく違います。そのうちパタッと電池がきれてしまわないか心配でした。
そんなときココロ貯金に出会い、子育て心理学カウンセラー養成講座を受けてみることにしました。
ココロ貯金による変化
今まで自分なりに考えて娘に接してきましたが、本当にこれでよいのか自信がありませんでした。なんとか進学をかなえてきたものの、同級生に比べてできていないことも多く、親としてどう接するべきかいつも迷ってきたのです。
講座を受講すると心のザワザワが薄れ、娘ができないことではなく、できることにフォーカスするようになった気がします。
よくしたのは「聴く」ココロ貯金。
大学の教授の話、授業の話、図書館司書の話……、娘は 30 分、1時間と話し続けるので、相槌をうちながらひたすら聴きました。
「触れる」貯金もしました。寝る前に寝転がって頭や足をマッサージしてあげたり、タイミングをみてぎゅっと抱きしめたり。
がんばりすぎて倒れてしまっては元も子もないので、「休む」ことを肯定的にとらえた関わりも心がけています。差しさわりのない日に学校を休んだときは、「よく計画を立てて休んだね。よかった、よかった」と、計画できたことにフォーカス。
機嫌が悪くて部屋にこもったときも、なるべくそっとしておきます。
ありのままの娘を認めていくうちに、前期は荒れて起伏が激しかった情緒が、後期になると見違えるように安定していきました。課題についても、前期はギリギリになってイライラしながらやっていたのが、1ヶ月前ぐらいから計画的にできるようになりました。
娘へのメッセージ
ある日、憤然とした表情で娘が言いました。
「いっぱい勉強したのに、どうしてもレポートがうまく書けない。くやしい」
—–あれ? “くやしい”っていう言葉を聞いたの、何年ぶりだろう。
くやしがる娘を横目に、わたしはひとり感慨にひたっていました。
ゼロか 100 かで判断し、できないことにフォーカスしがちだった娘は、今までなら「もうやりたくない」
「自分なんてこんなもの」とあきらめていたでしょう。
そんな娘に対し変わらず心がけてきたのは、できないことを「悲観的にとらえない」こと。
「ま、そんなこともあるよ」と軽く受けとめ、言葉の奥に
——今はできなくても「自分はダメ」だと思わなくてもいい
——ダメなときもあるけれど、また次にがんばればいいというメッセージを込めてきました。
負けん気みたいな、負けず嫌いみたいな、意欲があるからこそ生まれる“くやしい”という感情。
娘の口からこぼれた「くやしい」という言葉は、できない自分を否定するのではなく、「できるようになりたい」と願う向上心のあらわれに思えたのです。
——メッセージ、届いたね。
温かな感情がわたしを包み、一筋の希望の光がそっと心に差し込むのを感じていました。
おかあさんが実践したココロ貯金
・⾧い話も相槌をうちながら「聴く」
・頭や足のマッサージで「触れる」
・休むことを肯定的にとらえた関わり
・人と比べず、できることにフォーカス