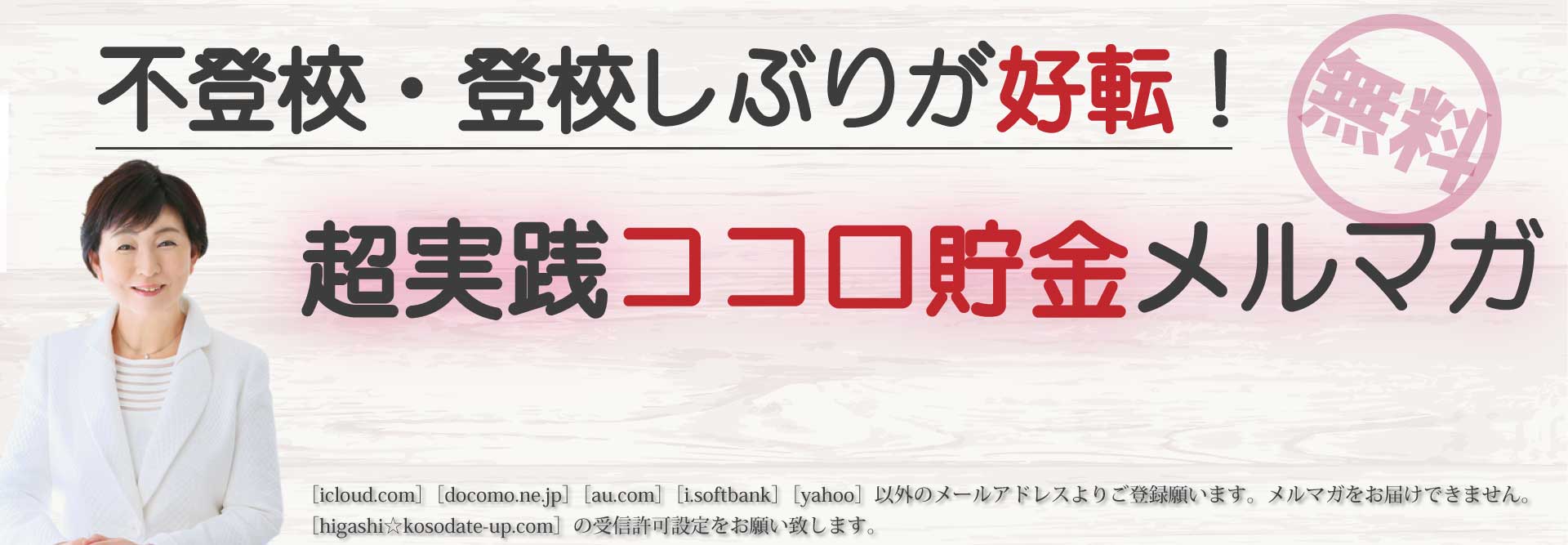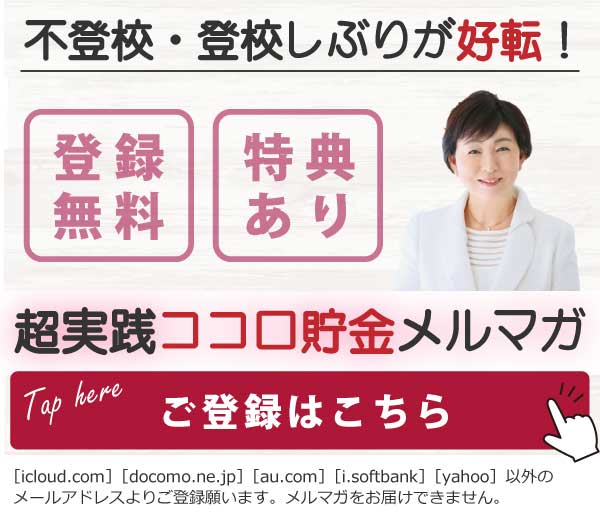体験談
体験談
息子の異変
「ちょっと様子がおかしいから見に来な」
涼しい秋風が吹きはじめた10月のある日、息子を預けている実家の父から連絡がありました。
息子は東大を目指して浪人中。幸いわたしの実家が東京にあったため、下宿しながら東京の予備校に通っていたのです。
しかし、浪人生活がはじまると同時にコロナが蔓延。会いたくても簡単には会えない状況でしたが心配でたまらず、緊急事態宣言のすき間をぬって、新幹線に飛び乗りました。
再会した息子は、頬がこけ目元もくぼんでいるように見えました。全身から緊張感がにじみ出ていて、追い詰められた心の内がひしひしと伝わってきます。
——父が気づいてくれて、本当によかった。
週末の3日間でなんとか彼を励ますと、一時は元気を取り戻したように見えました。けれども、それほど簡単なことではなかったのです。

【石橋やえさんのプロフィール】
2人のお子さんのお母さん。現在大学院の1年生の長男さんは、浪人生活がコロナ禍と重なり、精神的に落ち込みがちに。サポートの甲斐あって見事第一志望の東大に合格するも、学部内の激しい競争からメンタルダウン。やがて「うつ」の診断を受けてしまう。やえさんが子育て心理学カウンセラー養成講座を受講したのは、長男さんが浪人生の頃
息子の異変
「ちょっと様子がおかしいから見に来な」
涼しい秋風が吹きはじめた10月のある日、息子を預けている実家の父から連絡がありました。
息子は東大を目指して浪人中。幸いわたしの実家が東京にあったため、下宿しながら東京の予備校に通っていたのです。
しかし、浪人生活がはじまると同時にコロナが蔓延。会いたくても簡単には会えない状況でしたが心配でたまらず、緊急事態宣言のすき間をぬって、新幹線に飛び乗りました。
再会した息子は、頬がこけ目元もくぼんでいるように見えました。全身から緊張感がにじみ出ていて、追い詰められた心の内がひしひしと伝わってきます。
——父が気づいてくれて、本当によかった。
週末の3日間でなんとか彼を励ますと、一時は元気を取り戻したように見えました。けれども、それほど簡単なことではなかったのです。
コロナ禍の予備校生活
東大専門の有名なクラスに入学した息子。ところが、講義はすべてリモート授業です。前例のない事態なので仕方がないとはいえ、高い授業料に見合ったサポートが得られないような状況でした。
「こんな勉強の仕方で、大丈夫なんだろうか……」
わたしですらそう感じていたのですから、本人はどれほど不安だったことでしょう。さらに追い打ちをかけるように、担任の先生からこんな言葉をかけられたそうです。
「今年のクラスは出来が悪いから、受かるのは3割だな」
——それって、ほとんどの子が受からないってこと?
コロナの閉塞感と慣れない環境、そして将来への不安……。疑心暗鬼になりながらも必死に勉強を続けるうちに、息子の心は少しずつ追い詰められていったのだと思います。
息子、逃げ帰る
「疲れたから帰りたい」
息子から連絡があったのは、共通テストが目前に迫った12月のことでした。
——え? 何があったの?
動揺しながらも、努めて平静を装います。
「いいよ。帰っといで」
不安を悟られないように、いつも通りの声でそう返しました。
今、どんな気持ちでいるのだろう?
考えるたびに、胸の奥がぎゅっと締めつけられます。
里帰りの予定は約1週間。短い時間だけれど、わたしにできることを、できるかぎりしてあげよう——そう心に決めました。
5日間のココロ貯金
——とにかく、ココロ貯金を貯めよう。
ふだんは何もしてあげられない分、愛情を伝え、寄り添ってあげたい。
まずは、息子の好物を作って食べさせることから。
疲れた体を整えるために、整体にもつき添いました。
「共通テストまで日があるんだから、焦らなくて大丈夫。回復してから、がんばればいいじゃん」
整体師の先生の温かな励ましに、勇気づけられたようでした。
「日に当たりな」とも言われたので、毛布にくるまりながら、庭先で一緒に日向ぼっこ。
天気のよい日には、ちょっとしたドライブにも出かけました。近くの湖で東京にはない自然にふれて、ちょっと贅沢なホテルに寄ってケーキを食べて。
息子が「落ち着かないから」と勉強をはじめたときは、「 暇だったらピアノでも弾いてみたら?」と勧めてみました。今だけは勉強から離れ、リラックスした時間を過ごしてほしかったのです。
彼の奏でるピアノの音に耳を傾けながら、わたしの心は遠い日々へとさかのぼっていました。二人三脚でコンクールに挑んだあの時間。そう、あなたは昔から“がんばれる子”だったよね。
5日ほど穏やかに過ごしたところで、息子が言いました。
「そろそろ帰るよ」
再出発
息子を駅まで送った日。
ゆっくりと動き出す新幹線を見つめていたら、不覚にも涙があふれてしまいました。もし息子がひとりっ子だったら、きっと一緒に東京に行ったでしょう。でも、家には娘もいるし、仕事もある。
——がんばれ。頑張って。
どうか、体だけは大事にして。
結局、わたしにできるのは祈ることだけ。
精一杯の想いをこめて、手を振り続けました。
母のおにぎり
「お母さんのおにぎりが食べたい」
いつだったか、息子が言ったことがありました。梅干しやおかか、鮭などを入れたごく普通のおにぎり。けれど、彼にとっては何かが違うらしいのです。
そこで、たっぷりお米を炊いておにぎりをたくさん握って、冷凍して送ることにしました。いつも使っている塩がついた長い海苔も同封し、「ラップじゃなくてアルミホイルで巻いてね」というメッセージをひと言添えて。
子育て心理学カウンセラー養成講座で教わった「腹貯金」の遠隔バージョンです。授業の合間にお母さんのおにぎりを食べると、元気が出てくるんだよ——と、息子が笑って教えてくれました。
こうして、あの手この手で心と体を支えながら、浮き沈みの激しい日々を乗り越えていったのです。
そしてついに、第一志望だった東京大学に合格。
知らせを聞いたときは、心の底からホッとしました。
ところが——、
残念ながら穏やかな日々は、長くは続かなかったのです。
深夜の電話
第一志望の大学に合格し、念願のひとり暮らしをスタートさせた息子。
けれども、大学生活の1年目は、決して順風満帆ではありませんでした。
当時はまだ、コロナ禍の真っただ中。
友達と顔を合わせる機会もほとんどなく、外出するのは、かなりブラックだった塾講師のアルバイトのときくらい。
そのような環境の中で、息子のメンタルは徐々に落ち込んでいきました。
あの頃、わたしがよくしていたのは、「話を聴く」ココロ貯金です。
「夜、電話していい?」
ピコンと届くLINEのメッセージ。
「何時ごろ?」とたずねると「23時」と返ってきます。
23時から3時間……。日付が変わっても、息子の話は止まりません。
「もう、お母さん眠いんだけど……」と言いたい気持ちをぐっと飲み込み、相槌をうちながら、ひたすら耳を傾けました。
モヤモヤを吐き出すことで、少しでも心が軽くなるなら。
“安心できる場所”があると、少しでも感じてくれるなら——そう願いながら、話を聴き続けた日々でした。
見えなくなった未来
東大では、1・2年生の間は全員が「教養学部」に所属し、幅広く基礎的な知識を学びます。
そして2年生になると「進学選択(通称:進振り)」という制度で、3年生からの専門の学部を選ぶのですが——
この進振りの競争が、想像を超えるほど熾烈なのです。
息子が希望していたのは、人気の学部。
わずか5名の枠に、なんと400人が殺到したそうです。
結局、彼に与えられたのは「第8希望」だった学部。
あまりにも無残な現実に、体中の力が抜けてしまったようでした。
「なんのために、今までがんばってきたんだろう……」
そんなことを考えながら歩いていた通学中に、突然目の前が真っ白になり、そのまま倒れそうになったと言います。
「病院に行ったら、“うつ”って言われた」
彼の報告を聞いたわたしは、またしても東京行きの新幹線に飛び乗りました。
親子で過ごした週末
それから半年あまりは、月に一度のペースで、週末は東京の息子のもとへ通いました。
そうじや洗濯を手伝って、ごはんをつくったり、一緒に外食したり。向かい合って食事をしながら、たくさん話し合いました。
「例えばさあ、希望の学部に行くために、あえての留年ってアリかな?」
「うーん……アリかも。いや、やっぱりそれはナシかな」
会話を通して考えることで、息子の心は整理されていったのかもしれません。
胸に秘めた思いを言葉にしていくうちに、少しずつ前向きさを取り戻していきました。
その後の話
その後の息子は目立ったスランプもなく、3年生、4年生と、粛々と学業に打ち込みました。
そして——
驚いたことにあのとき息子は、大学院へのステップアップを考えはじめていたのです。
「やっぱり、本当にやりたい分野を学びたい」
そう考えた彼は院試に有利な研究室を自ら選び、しっかりと準備を重ね、見事に合格を勝ち取りました。
おそらく、わたしには想像もつかないような努力を重ねてきたことでしょう。
今は毎日がとても充実しているようで、忙しそうにしています。
心配は尽きないけれど
息子が巣立って、娘も成人しました。
「立派に育てられて」と言ってくださる方もいますが、正直なところ、まだまだ心配の連続です。
いくつになっても、子どもは子ども、母は母。
きっと、心配が尽きる日はこないのだと思います。
誰だって「がんばり続ける」のは、むずかしい。
心がポキッと折れそうになったとき、“ココロ貯金” を学んでいたから、息子は軽傷で踏みとどまれた。
そう感じています。
小さなつまずきをココロ貯金で乗り越えるたびに、息子の心の幹は少しずつ、太くなっていきました。
子ども自身がもつ力に感動し、その輝きに目を細めながら、いつまでも見守っていきたいと思います。
石橋やえさんが実践した“遠距離”ココロ貯金
・「否定せずに」話を聴く・息子が弱ったときには、即・上京
・会えたときには、てんこ盛りのココロ貯金
・おにぎりを冷凍して、宅配便で“腹貯金”
・電話では、3時間でも「聴く」貯金